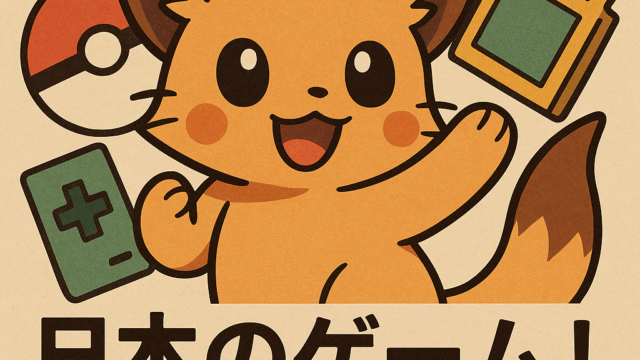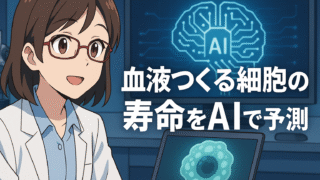「ステーブルコインって、仮想通貨とどう違うの?」
「円に連動するコインが出ると、私たちの生活にどんな影響があるの?」
近年、暗号資産(仮想通貨)という言葉は広く知られるようになりましたが、その中でも「ステーブルコイン」という新しい存在に注目が集まっています。2025年秋には、国内初となる円建てステーブルコイン「JPYC」が発行される予定です。金融庁が正式に承認するというニュースは、日本の金融とデジタル通貨の歴史において大きな転換点といえるでしょう。
本記事では、ステーブルコインの基本から、国内外の最新動向、そして私たちの生活やビジネスにどんな変化をもたらすのかを、わかりやすく解説していきます。
ステーブルコインとは何か?
ステーブルコインは、その名の通り「価値が安定しているコイン」を意味します。
通常の仮想通貨(ビットコインなど)は価格の変動が大きく、投資対象としては魅力があっても「日常の決済手段」としては不便でした。
そこで登場したのが、法定通貨(ドルや円など)と価値を1対1で連動させるステーブルコインです。
例えば「1JPYC=1円」という仕組みであれば、価格変動のリスクがほとんどなく、安心して送金や決済に使えるようになります。
日本での動き:JPYCの誕生
2023年6月に施行された改正資金決済法により、ステーブルコインは「通貨建て資産」として法的に定義されました。これにより、銀行・信託会社・資金移動業者が発行できるようになったのです。
そして2025年秋、フィンテック企業のJPYC株式会社が「JPYC」という円建てステーブルコインを発行予定です。
このコインは、預金や国債といった流動性の高い資産を裏付けとして保有し、1JPYC=1円の価値を保ちます。
利用者は代金を振り込み、電子ウォレットにJPYCを受け取る形で利用できます。これにより、
- 留学生への仕送りなど国際送金
- 法人間の決済
- ブロックチェーン上の資産運用(DeFi)
など、多様な用途が広がります。
JPYCは今後3年間で1兆円分の発行を目指しており、国内外の投資家から関心が寄せられています。
世界のステーブルコイン事情
世界ではすでにドル建てのステーブルコインが大きく普及しています。代表的なのが、
- USDT(テザー社)
- USDC(米サークル社)
この2つが市場の大半を占めています。2025年時点で市場規模は2500億ドル(約37兆円)を超えており、米シティグループは「2030年までに最大3.7兆ドル(約540兆円)に成長する」と予測しています。
また、各国も規制整備を進めています。
- 米国:2025年7月「GENIUS法」が成立し、発行や管理ルールを明確化
- 香港:2025年8月「ステーブルコイン条例」を施行し、人民元建ての発行環境を整備
このように、各国が競うようにステーブルコインの基盤づくりを進めており、日本のJPYC発行もその流れの中で大きな一歩といえます。
ステーブルコインがもたらす未来
ステーブルコインが普及すると、私たちの生活やビジネスにはどのような変化が起こるのでしょうか。
- 国際送金の低コスト化
従来の銀行送金は数日かかるうえ、手数料も高額でした。ステーブルコインなら、数分で低コスト送金が可能になります。 - EC・決済サービスの拡大
米国ではすでに大手決済企業ストライプやコインベースがステーブルコイン決済を導入。日本でも同様のサービスが広がる可能性があります。 - 資産運用の新しい選択肢
ブロックチェーン上の分散型金融(DeFi)では、ステーブルコインを活用したレンディングや投資が可能。安全性と流動性を兼ね備えた資産運用が広がります。 - 企業の資金管理に変革
大企業だけでなく中小企業も、為替リスクを抑えつつ国際取引をスムーズに行えるようになります。
課題と今後の展望
もちろん、課題も存在します。
- 発行体の信頼性の確保
- 不正利用やマネーロンダリング対策
- 利用者保護のための規制整備
これらをどう解決していくかが、普及の鍵となります。
一方で、国内外の金融機関やフィンテック企業はすでに積極的に動いており、ステーブルコインを活用した新しいサービスは今後ますます増えていくと見られます。
まとめ
ステーブルコインは「仮想通貨の利便性」と「法定通貨の安定性」を兼ね備えた新しいデジタル資産です。
2025年秋に登場する「JPYC」は、日本におけるステーブルコイン普及の第一歩となるでしょう。
国際送金や決済の利便性向上だけでなく、私たちの投資・資産運用、そして企業活動にも影響を与える可能性があります。
今後の動向に注目しつつ、身近な金融サービスの変化を見守っていきたいところです。