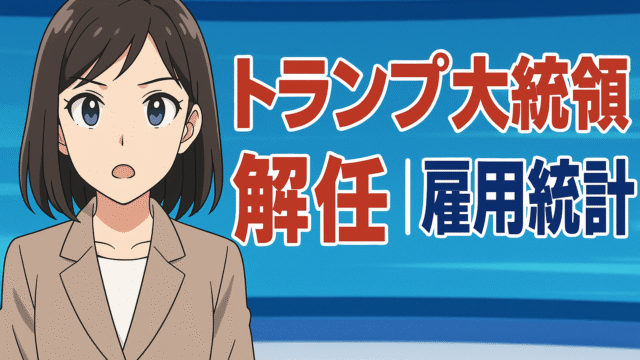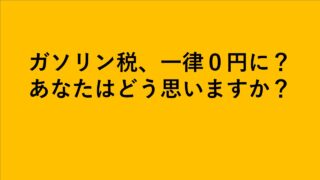皆さんは、ニュースサイトやSNSで見た写真に「これって本当に本物なのかな?」と思ったことはありませんか?
いまや、AIを使えば誰でも簡単にリアルな合成写真を作ることができます。一見すると本物そっくり。でも、実は全く別の映像だった……なんてことも珍しくありません。そんな中、ニュースに使われる「報道写真」の信頼性をどう守るかが、大きな課題になっています。
この問題に、ある日本企業が新しいアプローチで挑み始めました。
ソニーが始めた“写真の真偽”確認サービス
2025年6月、ソニーは「報道に使う写真が本物かどうか」を、誰でも確認できる新しいサービスを発表しました。
ポイントは、撮影の瞬間に“電子署名”を埋め込むという独自の仕組み。これにより、「いつ・誰が・どのカメラで撮ったか」といった情報が写真に残り、あとから改ざんされたかどうかもすぐにわかるのです。
このサービスに対応しているのは、ソニーの一部のカメラ、たとえば「α1 II」など。これらのカメラで撮影された写真には、撮影時点で自動的にデジタル署名が付きます。そして、その署名が改ざんされていないかを、外部の人でも専用サイトを通じてチェックできるようになりました。
つまり、新聞社やテレビ局が通信社から報道写真を購入する際、「これはAIで作られたものではないか?」「後から加工されていないか?」といったことを、客観的に確認できるというわけです。
加工写真と“本物”の境目があいまいな時代に
近年は、生成AI(ジェネレーティブAI)を使って、まるで本物のような写真や映像が作れるようになりました。SNSでは、フェイク写真がバズってしまい、真実とは違う情報が広まることもあります。
たとえば、ある災害現場の写真が「現場の状況を示す証拠」として拡散されたものの、実は全く別の場所をAIで再現した画像だった──。そんなフェイクが信じられてしまうのは、写真が本物かどうかを見抜くのが非常に難しいからです。
これまでは、「信頼できるメディアが使っている写真だから大丈夫だろう」と考えられてきました。でも、その信頼を支えるには、“目で見ただけではわからない”部分の保証が必要になってきています。
新しい信頼のかたち──透明性がもたらすもの
今回のソニーのサービスは、これまで報道機関の内部でしか確認できなかった“撮影証明”を、外部の人でもチェックできるようにする点が画期的です。
たとえば、新聞社が自社のウェブサイトに「この記事の写真は、こちらで真偽を確認できます」というリンクを貼ることで、読者も自分で写真の信頼性を確かめられるようになります。
これは、報道機関と読者の“信頼の橋渡し”となる可能性を秘めています。
さらに、2025年秋には、写真だけでなく動画にも対応した検証サービスの開始が予定されています。動画に対しても「誰が撮影し、どこを編集したか」を確認できるようになれば、ニュース映像やドキュメンタリーにおいても透明性が格段に向上するでしょう。
これからの報道と、私たちの見かた
もちろん、この技術が導入されたからといって、すべての写真がすぐに“安心”になるわけではありません。電子署名に対応していないカメラや、すでにネット上に出回っている画像は対象外です。また、使うかどうかは報道機関の判断に委ねられます。
それでも、今回のような技術が登場したことは、「写真を信用できるか?」という問いに、ひとつの答えを出そうとする大きな一歩です。
写真や映像が持つ「リアルさ」は、私たちの感情を動かし、意識や社会を変える力を持っています。だからこそ、その“リアル”が本当に本物なのかを、誰もが確認できる仕組みは、今後ますます重要になっていくでしょう。
最後に
「この写真は本物ですか?」
これまでなら、その答えは見る人の“信じる心”に頼っていたかもしれません。でも、これからは技術の力で、それを証明できる時代になりつつあります。
私たち一人ひとりも、ただ情報を受け取るだけでなく、**その裏側にある「信頼の証拠」**を知ることで、より賢くメディアと付き合えるようになるかもしれません。
ソニーの新しい挑戦が、メディアの未来にどんな変化をもたらすのか──これからの報道の姿を、ぜひ一緒に見届けていきましょう。