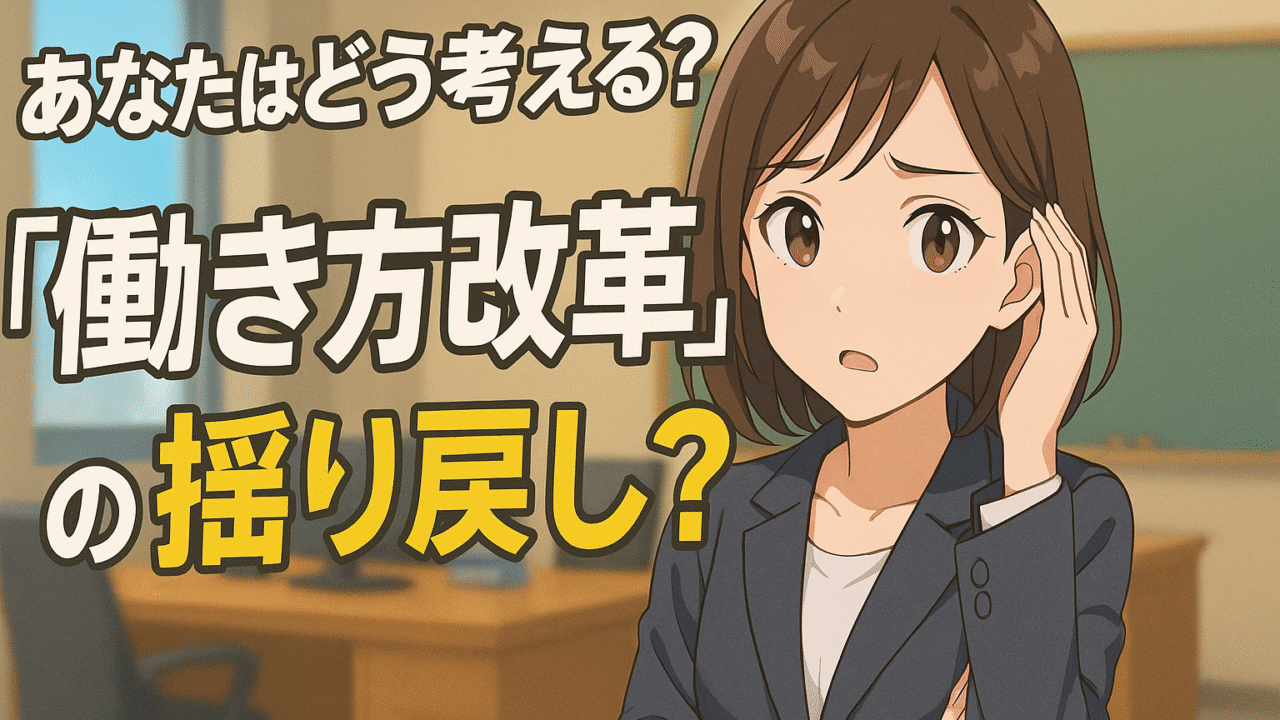あなたは、もっと働きたいですか?
それとも、もっと自分の時間を大切にしたいと思いますか?
ここ数年、日本社会で繰り返されてきた問いが、今ふたたび揺れ動いています。それは、「働き方改革」と呼ばれる国をあげた取り組みに関してです。2019年に施行された「働き方改革関連法」によって、労働時間の上限規制や年次有給休暇の取得義務化といった新しいルールが整備され、多くの職場で“長時間労働の是正”が進められてきました。
しかし今、その流れに“揺り戻し”とも言える動きが出ています。
「もっと働きたい」という声の裏にあるもの
2025年の選挙を前に、与党をはじめとする一部の政党は、「働きたい改革」というスローガンを掲げ、労働時間の上限緩和などを提案しています。背景にあるのは深刻な人手不足。特に介護や建設、小売・飲食といった業界では、十分な人員を確保できず、業務に支障をきたしている現実があります。
「もっと働ける人には働いてもらおう」という発想自体は、ある意味合理的に聞こえます。しかし、それが「もっと働かせたい」という経営者の都合にすり替わるとしたら、話は別です。
働き方改革の専門家である小室淑恵さんは、「働きたい改革の裏には、“評価の格差”や“暗黙の強制”というリスクが潜んでいる」と警鐘を鳴らします。つまり、「もっと働きたい」と手を挙げた人が“やる気がある人”と評価されるようになれば、反対にそうでない人が“不熱心”と見なされる。結果的に、誰もが過剰な労働を強いられる構造が生まれる危険があるというのです。
過労死遺族の声から見える、現場のリアル
こうした懸念は、現場で起きている問題にも重なります。過労死した医師の母である高島淳子さんは、「やる気が評価される社会では、働かない選択が“非協力”と見なされる。同調圧力やパワハラが生まれやすくなる」と訴えます。
働き方改革の目的は、単なる労働時間の短縮ではなく、「誰もが安心して働ける環境をつくること」です。過労死という悲劇を繰り返さないためにも、改革の本質を見失ってはならないのです。
DXと多様な人材こそが、人手不足解消のカギ
では、人手不足の解決策として、労働時間を延ばす以外にどんな手段があるのでしょうか?
京都大学の柴田悠教授は、「残業を増やすのではなく、DX(デジタルトランスフォーメーション)によって生産性を高めるべき」と提言します。つまり、限られた人材で効率よく業務を回す仕組みを作り、必要な労働量そのものを減らす努力が必要なのです。
さらに注目されているのが、「多様な労働力」の活用です。高齢者、育児中の親、介護を抱える人たちなど、これまで働くことが難しかった人々にも、短時間勤務やテレワークなどを通じて参加してもらう。このような柔軟な働き方が可能になれば、労働力人口を拡大することができるのです。
そのためには、企業側の意識改革も欠かせません。たとえば、「時間外割増賃金」を引き上げることで、残業を“コスト”として扱い、安易に社員に負担をかけない仕組みを整えることも、有効な一手となるでしょう。
若者の意識が示す「新しい働く価値観」
厚生労働省の調査によれば、18~25歳の若年層の約8割が「キャリアとプライベートの両立」を重視していると答えています。もはや“仕事一筋”は過去の価値観。今の若者たちは、趣味や家族、学び直しといった私的な時間も大切にしながら、自分らしく働くことを求めています。
そのような時代に逆行するような労働環境では、優秀な人材は企業に定着しません。働きやすさを重視することは、単なる“福利厚生”ではなく、経営戦略そのものだと言えるのです。
おわりに──“改革”の本当の意味を、もう一度考えよう
働き方改革とは、労働時間を減らすことでも、労働力を増やすことでもなく、「誰もが尊厳をもって働ける社会をつくること」ではないでしょうか。
「もっと働きたい」という声が尊重される一方で、「無理せず働きたい」「家庭や健康も大切にしたい」という声も同じように大切にされる社会。それが、すべての人にとって持続可能な「働き方」の未来をつくる鍵となります。
今こそ、“改革”の本当の意味を、私たち一人ひとりが考えるときなのかもしれません。