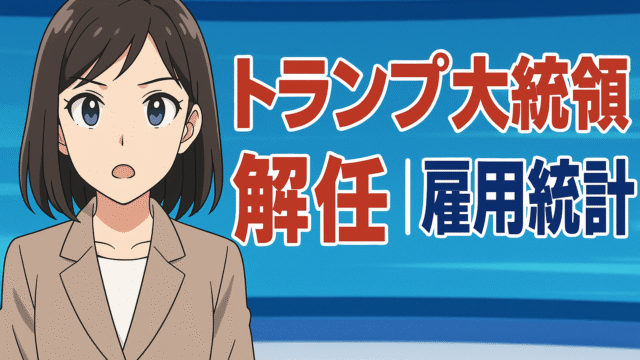「なぜ最近、会社の報酬制度が話題になっているの?」
そう疑問に思った方もいるかもしれません。実はいま、日本企業の「人材の引き留め方」が大きく変わりつつあるのです。
そのキーワードが、“テック大手並みの報酬制度”。
聞き慣れない言葉かもしれませんが、これは単なる給料アップではありません。株式報酬という、新しいインセンティブの仕組みが背景にあるのです。
たとえば、日立製作所という日本を代表する大企業が、まさにこの変化の最前線に立っています。今回はその日立の事例をもとに、「なぜ日本企業がテック大手のやり方を取り入れようとしているのか?」を、やさしく解説していきます。
■ 報酬が“お金”だけじゃない時代に
これまでの日本企業では、年功序列やボーナスなど、比較的安定した報酬体系が主流でした。しかし近年は、そうした仕組みだけでは人材を引き留めるのが難しくなっています。
特にITやAIなどの分野では、優秀な人材の争奪戦が激しくなっており、報酬制度に工夫が求められています。
ここで注目されているのが、「RSU(譲渡制限付き株式ユニット)」という仕組みです。
■ RSUってなに?ストックオプションとの違い
RSUは、一定の条件を満たすと会社から株式が無償で与えられる制度です。
たとえば、3年働き続けた社員に対して、その会社の株式を一定数プレゼントする、というイメージです。
よく似た制度に「ストックオプション(SO)」があります。こちらは「将来的に、今の価格で会社の株を買える権利」です。しかし株価が下がると利益が出ず、魅力が薄れることも。
その点、RSUは株価にかかわらず一定の価値を持ちやすいため、従業員にとっても安心感があります。
■ なぜ日立が導入?その背景とは
日立は、これまで取締役や役員に対してのみRSUを導入していましたが、2026年度から管理職層にも広げると発表しました。
本部長や事業部長クラス、さらには子会社の社長なども対象にし、2027年度には約1500人まで拡大する予定です。
この背景には、世界的な人材獲得競争の激化があります。特にアメリカやドイツなどのテック企業では、RSUの導入が一般的で、優秀な人材がそうした企業へ流れてしまうことも少なくありません。
日立としても「世界で戦うには、それ相応の報酬制度が必要だ」と考えているのです。
■ ソニーも同様の動き、他社の導入事例
日立だけではありません。ソニーグループも2022年にRSU制度を導入し、2024年度は約4100人に、平均で710万円分の株式を付与しています。
さらに、アメリカの子会社では「税制適格株式購入プラン」という新制度をスタートさせようとしています。これは、希望する従業員が市場価格より安く自社株を買える制度で、税制上の優遇も受けられるという仕組みです。
このように、「自社株を使って人材を引き留める」動きは、すでにグローバルでは一般的なのです。
■ 法制度の壁と、その先にある未来
しかし、日本ではRSUの導入にいくつかの課題もあります。
現在の日本の会社法では、会社が保有する株を無償で渡せるのは、原則として取締役や執行役に限られています。
そのため、従業員にRSUを付与するには、いったん“お金(=金銭債権)”という形にしてから株に交換する必要があり、手続きが煩雑なのです。
こうした法的なハードルを乗り越えるため、法務省の諮問機関も「制度改正の可能性」を議論し始めています。もしこの規制が緩和されれば、日本でもRSUの導入が一気に進むかもしれません。
■ 報酬は「働きがい」と「未来の選択肢」になる
報酬制度の見直しは、単にお金を増やす話ではありません。
従業員が「この会社で長く働きたい」と思える仕組みであること。自分の働きが、会社の成長につながり、それがまた自分に返ってくるという実感。
それを可能にするのが、株式を用いた報酬制度なのです。
いま、日本企業は大きな転換点に立っています。果たして、テック大手並みの報酬制度は、日本の働き方をどう変えていくのか?
日立やソニーのような動きは、今後多くの企業に波及していくことでしょう。
■ まとめ:未来の報酬制度は「選ばれる会社」への鍵
働き方が多様化する中で、報酬制度もまた多様であるべき時代になりました。
給与やボーナスだけではない、新しい「価値の提示」が、優秀な人材を惹きつけ、そしてつなぎとめます。
「会社の未来に貢献することが、自分の未来を豊かにする」
そんな感覚を、制度として形にしたRSUや株式報酬は、今後の企業競争力において欠かせない武器になるはずです。
あなたの働く会社は、どんな報酬制度を用意していますか?