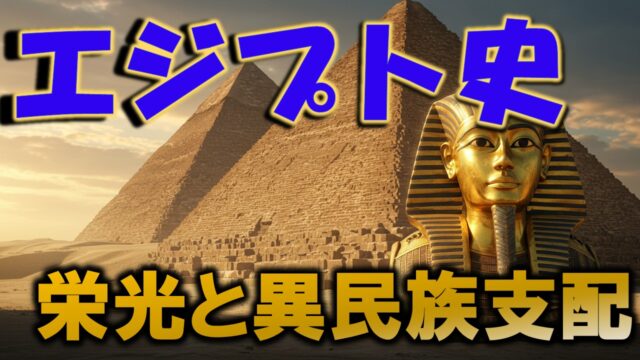皆さんは、毎朝鏡に向かってする「化粧」が、いつから始まったかご存知ですか?
もしかしたら、「最近になって始まったこと」だと思っている方もいるかもしれません。しかし、実はその歴史は紀元前からはるか昔にまでさかのぼり、美しさだけでなく、時に健康や身分、文化までも象徴する、奥深いものでした。
この記事では、そんな「化粧の歴史」を紐解きながら、時代とともに移り変わる人々の価値観や知恵をご紹介します。2000文字程度で、皆さんが普段何気なく手にしている化粧品が、どれほどの歴史を背負っているのか、その物語を一緒に辿っていきましょう。
WordPress用記事:化粧の歴史:紀元前から現代までを旅する、美のタイムカプセル
1. 美しさの始まり:古代エジプトと砂漠の知恵
化粧の歴史は、今からおよそ紀元前1200年代、古代エジプトにまでさかのぼります。ツタンカーメンの黄金のマスクに見られる目の周りのアイラインは、単なる美しさのためだけではありませんでした。
当時のアイラインの原料は、紺色の鉱石「ラピスラズリ」を粉末にしたもので、これを液体に溶かして使用していました。これには、強い日差しから目を守るだけでなく、病気を媒介する蚊やハエを寄せ付けない「虫除け」としての意味合いも含まれていました。
また、肌には黄色の顔料を塗って日焼け止めにしたり、香油で乾燥した皮膚をやわらかくしたりと、砂漠地帯ならではの知恵が詰まった化粧が行われていました。これらの化粧はやがて、神官などの特権階級のシンボルとなっていきました。
「白い肌は肉体労働をしていない証拠」として、鉛白を使った白い化粧もこの時代に始まり、その毒性が知られてもなお、18世紀まで続くことになります。
2. 自然な美しさを求めた時代:古代ギリシアとローマ
古代ギリシアでは、日々の鍛錬によって培われる《肉体そのものの美しさ》こそが真の美とされました。そのため、表面的な美しさである化粧はあまり評価されませんでした。
一方、古代ローマでは、ギリシアほどではないものの、アレクサンドロス3世の東征によって流入したオリエントの文化の影響で、上流階級の間で鉛白を使った化粧が行われました。紀元2世紀には、現在のコールドクリームの原型が作られたとも言われています。
3. 信仰と化粧の葛藤:中世ヨーロッパ
中世ヨーロッパでは、キリスト教の教えが化粧文化を一時的に廃れさせました。「神がお作りになったものに手を加えてはならない」という考え方と、「虚飾は罪である」という教えが強く、公然と化粧をすることはできなくなりました。
しかし、それでも特権階級の人々は「白い肌」を保つために様々な努力をしました。ビールで顔を洗ったり、眉を剃って顔の白さを強調したり、極端な場合は瀉血(血を抜くこと)で人為的に貧血状態にして肌を白く見せることまで行われました。
4. 化粧文化の復活と科学の進歩:近世・近代ヨーロッパ
16世紀の宗教改革でカトリック教会の力が弱まると、化粧は再び流行します。この流行のきっかけは、イギリスの女王エリザベス1世とされています。
彼女は、顔に蜜蝋を塗り、その上から鉛白のおしろいを叩くという化粧をしました。しかし、この化粧は溶けやすく、冬でも暖房に近づけませんでした。さらに、鉛中毒によるシミ(肝斑)ができやすく、それを隠すために「つけぼくろ」が流行しました。
16世紀には水銀を使ったおしろいも登場し、肌の古い角質が剥がれることから人気を博しましたが、これも水銀中毒により歯茎が黒ずんだり、歯が抜けたりする副作用がありました。このため、口元を隠すために扇子が流行しました。
18世紀になると自然志向が強まり薄い化粧が流行し、19世紀には病的な美しさを理想とする時期もありました。しかし、1899年には人体に無毒な酸化亜鉛を使ったおしろいが開発されるなど、科学の進歩が化粧をより安全なものへと変えていきました。
5. 日本独自の美意識:日本の化粧文化史
日本でも独自の化粧文化が発展しました。3世紀頃には、呪術的な意味合いで硫化水銀や酸化鉄などの赤い顔料を体に塗る風習がありました。
飛鳥時代には、遣隋使によって大陸から化粧品が伝わり、鉛を使ったおしろいが作られるようになりました。
平安時代には、唇や頬に薄く紅をさすことが美意識とされ、口紅に関する記述も見られます。また、公家や武士の間でも、身分の象徴としておしろいや眉化粧が定着しました。
江戸時代になると、化粧は上流階級だけでなく庶民にも広まり、世界で初めて庶民向けの化粧品店が開かれました。当時の女性の化粧は、水おしろいを肌に塗り、中心に口紅をさすといったものでした。
特筆すべきは「お歯黒」の文化です。これは平安時代から始まり、江戸時代には既婚女性の習慣となりました。貞節の証とされましたが、タンニンの効果で歯槽膿漏の予防にもなっていたと言われています。
6. 現代への架け橋:明治・大正から現代
明治時代になると、政府の「お歯黒引眉禁止令」が発令され、西洋化が進む中で日本の伝統的な化粧文化は少しずつ姿を変えていきます。しかし、鉛白粉の害が論じられつつも、その優れた使用感から昭和初期まで使われ続けました。
大正時代には、和と洋を組み合わせた「和洋折衷」の化粧が流行。関東大震災後には「モダンガール」と呼ばれる女性たちが、アイシャドウや唇全体に塗る口紅といった西洋風の化粧を取り入れるようになりました。
20世紀後半になると、健康的な肌色やアイメイクが重視されるようになり、1970年代後半からは個性を生かす「ナチュラルメイク」が市民権を得ました。
現代では、ナチュラルメイクが主流となりつつも、ジェンダーレスの観点から化粧をする男性が増えるなど、その価値観はさらに多様化しています。
この化粧の歴史について、さらに詳しく知りたい方は、こちらの動画も参考にしてみてください。より視覚的に、歴史の流れを理解できるはずです。
YouTube動画:化粧の歴史について https://www.youtube.com/watch?v=0
皆さんの日々の化粧に、新たな視点が加わったのではないでしょうか?化粧は、単なる美の道具ではなく、その時代の文化や社会、そして人々の生き方を映し出す鏡なのです。