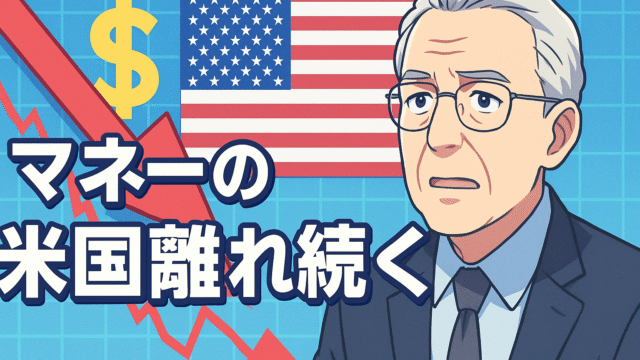私たちが美術館で目にする名画には、長い時間の中で積み重なった「損傷」と、それを救うための「修復」というもう一つの物語があります。
本記事では、600年にわたる油絵の技法の歴史をたどりながら、現代で進化し続ける最新の絵画修復技術について紹介します。
油絵の誕生と、テンペラからの転換
油絵の歴史は約600年あります。
それ以前の西洋絵画は「テンペラ」という卵黄を使った絵具が主流でした。
テンペラは発色は美しいものの、乾燥が速く、なめらかなグラデーション表現が難しいという問題がありました。
そこで、15世紀に登場したのが「油絵具」です。
油絵は乾燥が遅く、色を重ねることで深い陰影や光の表現が可能になり、絵画表現は大きく変化しました。
フランドル技法(15世紀・ファン・アイク)
油絵初期に確立したのが「フランドル技法」。
ファン・アイクが代表的な画家です。
特徴
- 白い下地(白亜地)の上に精密な下絵を描く
- 明るさは「白の絵具」ではなく「下地の白を残すことで表現」
- 透明色を多用し、光を透かすような美しい仕上がりになる
白の絵具は時間とともに黄変しやすいですが、フランドル技法は下地の白を活かしているため、現代でも美しさが保たれています。
フィレンツェ技法(15世紀末)
フィレンツェでは、油絵とテンペラの両方を組み合わせた技法が多く見られました。
主に板の上に石膏地を敷いた支持体が使われました。
油絵の深みとテンペラの明るさを両立した時代です。
ヴェネツィア技法(16世紀)
16世紀、ヴェネツィアでキャンバスが広く使われ始めます。
帆布が海洋国家ヴェネツィアで大量に手に入ったためです。
特徴
- キャンバスにより大画面制作や輸送が容易に
- 下地は赤褐色
- 明るい部分にシルバーホワイトを使用
- 色の重ね塗りが容易となり、自由な表現が可能に
ただし、シルバーホワイトは経年で透明化し、絵が暗くなることが現在でも確認されています。
ルーベンス技法(17世紀)
ルーベンスは、絵が暗くくすむ問題に気づき、下地を明るい灰色や黄色に変更しました。
特徴
- 明るい下地に薄い茶色で影を描く
- 筆致が大胆
- 制作スピードが非常に速かった
同時代のレンブラントやベラスケスも、赤褐色の下地を使いつつ、暗くなることを見越して明るく描いています。
現代の修復技術:デジタル・ラミネートマスク法
近年、絵画修復の現場ではデジタル技術が台頭しています。
マサチューセッツ工科大学の Alex Kachkine による研究では、デジタルで構築したラミネートマスクを使って絵画を修復する方法が報告されました(Nature 2025掲載)。
修復手順
- 損傷した絵画を高解像度でスキャンし、デジタル上で復元
- 必要な色の情報をマスクとしてラミネートシートに印刷
- そのマスクを絵画の表面に貼り付けて仕上げる
メリット
- 作業時間が大幅に短縮(数ヶ月 → 数時間)
- マスクは取り外し可能で、元の絵を傷つけない
現時点での制約
ただし、現時点では表面が滑らかなニス塗りの絵画に限定されます。
凹凸のある絵肌には密着できないため、今後の改善が期待されています。
まとめ
油絵は600年の歴史の中で、技法も保存方法も進化を続けてきました。
そして今、最新のデジタル修復技術が、再び名画を蘇らせようとしています。
「過去の技術 × 現代の科学」
この融合が、生き残るべき作品を未来へと引き継ぐ鍵となるでしょう。
参考文献
Kachkine, A. Physical restoration of a painting with a digitally constructed mask.
Nature 642, 343–350 (2025).
https://doi.org/10.1038/s41586-025-09045-4