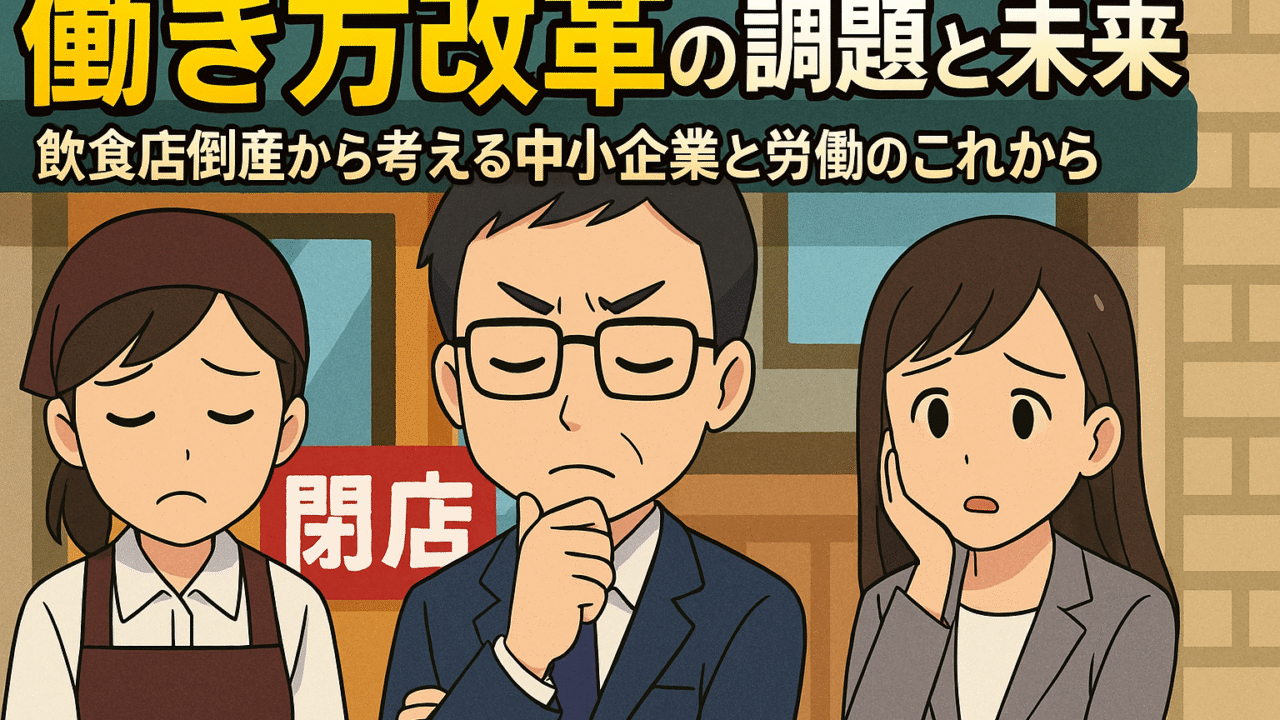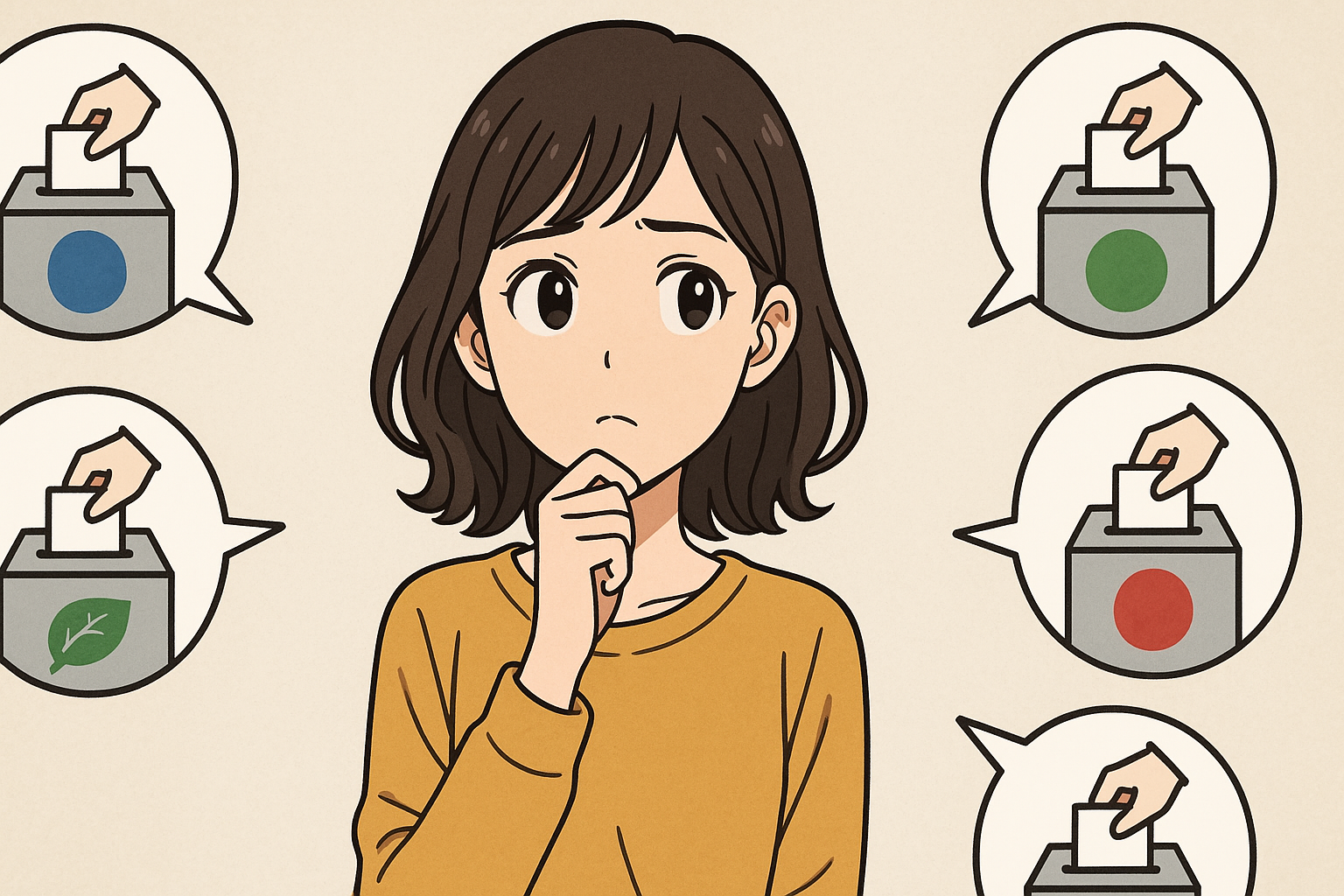――飲食業の倒産から見えてきた、“働き方改革”の本当の課題とは
「最近、近所の飲食店が次々と閉店している気がする…」
そんな声を耳にしたことはありませんか?
実はそれ、気のせいではありません。帝国データバンクが発表した調査によると、2025年上半期(1月〜6月)に倒産した飲食店の数は、なんと458件。これは前年同期比で5.3%の増加であり、上半期としては過去最多という深刻な数字です。このペースで進めば、年間倒産数は900件を超える可能性もあると言われています。
では、なぜ今、飲食店の倒産が相次いでいるのでしょうか。
そして、その背景にある「働き方改革」とは、どのように関係しているのでしょうか。
「人がいない」「コストが高い」…中小飲食店の苦悩
倒産の要因としてまず挙げられるのは、「コロナ禍のダメージ」からの完全な回復が難しいという現実です。営業制限や来店客数の激減により、資金繰りに苦しんできた飲食店は多く、その傷が癒えきらないまま次の波が押し寄せてきました。
それが、食材費・人件費・光熱費などの高騰です。
例えば、人件費。2023年以降、日本全体で「賃上げ」が強く求められるようになり、最低賃金の引き上げや正社員登用の推進が進められています。これは「働き方改革」の流れの一部であり、労働者の権利保護や生活の安定に向けては歓迎されるべき方向です。
しかしその一方で、小規模な飲食店にとっては重すぎる負担となるケースも少なくありません。「人を雇いたくても雇えない」「社員を増やせば赤字になる」。そんな声が現場からは上がっています。
「働き方改革」は、誰のための改革か?
2019年に施行された「働き方改革関連法」によって、時間外労働の上限規制や有給休暇取得の義務化が導入され、日本社会は「過労をなくす」方向へと大きく舵を切りました。
これは多くの労働者にとって、非常に重要な前進だったことは間違いありません。過労死や長時間労働による健康被害が問題化するなかで、「働きすぎない社会」は一つの理想でもありました。
しかし、今その“理想”が、別の問題を生んでいるという指摘もあります。
特に、人手不足が深刻な中小事業者にとっては、「労働時間の制限」や「賃上げの義務化」が経営を圧迫する要因となっており、働き方改革が進めば進むほど、働く場そのものが減ってしまうという“逆説的”な現象が起きているのです。
一方、大手チェーンは好調──なぜ?
こうした苦境にある中で、大手外食チェーンの業績は好調です。
たとえば、すかいらーくホールディングスでは、2025年6月の既存店売上高が前年同月比3.9%増と、39カ月連続で前年実績を上回っています。日本マクドナルドも同じく、6カ月連続のプラス成長。
この違いは何か。
一言でいえば、「体力の差」です。
大手は人材確保にもIT活用にも資本投下できる余裕があります。たとえば、シフト管理や予約の自動化、キッチン業務の効率化などを通じて、少人数でも高い生産性を維持する仕組みが整えられているのです。
また、従業員の働き方にも柔軟性があります。時短勤務、子育て中の社員の支援、週休3日制の導入など、従業員満足度と生産性を両立させる工夫が各社で進んでいます。
働き方改革は「余裕」があってこそ成立する
ここまで見てきたように、働き方改革の理念は正しくても、それを実現するには「人的・経済的な余裕」が必要です。つまり、余力のある企業しか“改革”を実践できないというのが現実です。
だからこそ今、求められているのは「改革の再設計」ではないでしょうか。中小企業が倒れ、大企業だけが生き残る社会では、私たちの暮らしの選択肢がどんどん狭まっていってしまいます。
働く側・雇う側、どちらにも「持続可能な」改革を
では、どうすればいいのでしょうか。
一つの鍵は、「持続可能性」の視点です。
雇う側にとっても、働く側にとっても無理のない制度設計が必要です。たとえば、最低賃金引き上げと同時に、中小企業向けの補助金制度を充実させる。あるいは、育児・介護中の人も無理なく働ける仕組みを業界全体で整える。
もう一つ重要なのは、ITとDXの活用です。人手が足りないなら、業務を減らす工夫をする。業務を見直し、無駄を削り、機械に任せられる部分は機械に任せる。これができるようになれば、少人数でも安定経営が可能になります。
結論:働き方改革の“次のステージ”へ
「働き方改革」は終わったわけではありません。むしろ今こそ、第二ステージに進むべき時です。
それは、**“理想論”ではなく、“現実と向き合う改革”**へと舵を切ること。
大企業だけが恩恵を受けるのではなく、小さな店、小さな雇用、小さな希望も守れる社会を目指すべきなのです。
あなたの働き方は、どうでしょうか?
改革の波に飲まれていないでしょうか?
そして、どんな未来の働き方を望みますか?
その問いへの答えが、これからの日本社会を形作る一歩になるはずです。