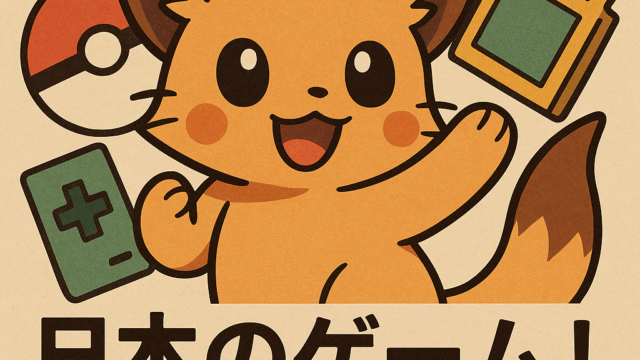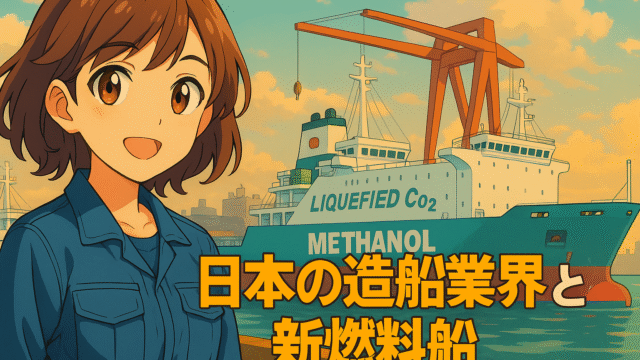「物価は上がっているのに、どうして金利は据え置きなんだろう?」
そんな疑問を抱いたことはありませんか?
2025年の夏、日本銀行(以下、日銀)とアメリカの中央銀行・FRB(連邦準備制度理事会)は、共に政策金利を据え置く決定を下しました。
一見すると「何もしていない」ように見えるこの判断の裏には、国際政治や経済の複雑な事情が絡み合っています。
この記事では、最新の金融政策の動きと、その背景にある「なぜ動かないのか?」という問いに、わかりやすくお答えします。
日銀とFRB、正反対の動き?実は共通点も
まず前提として、日銀とFRBの金融政策は現在、真逆の方向にあります。
- 日銀:2024年3月にマイナス金利を解除し、利上げに向かう局面に
- FRB:2024年9月から利下げ局面に突入
それにもかかわらず、2025年7月の政策会合では、どちらも金利を据え置くという同じ判断をしました。
これは偶然ではありません。両者とも、「先が読めない」状況に慎重になっているのです。
キーワードは「関税」と「物価」
動きを止めた最大の理由は、アメリカの関税政策です。
トランプ政権が再び導入した高関税が、モノの価格や経済全体にどう影響するのかを、両国の中銀は慎重に見極めようとしています。
FRBのパウエル議長は記者会見で、こう述べました。
「関税の影響は、想定よりも長引く可能性がある」
つまり、今すぐ利下げしてしまうと、あとでインフレがぶり返したときに対応が遅れるかもしれない。
一方で、日銀の植田総裁も同じように、関税が企業収益や賃金、物価にどう波及するのかを「じっくり見極めたい」としています。
日本の物価、アメリカの消費、それぞれの事情
ここで、日米の足元の経済状況も見ておきましょう。
日本の物価は「食品中心に高止まり」
特にコメなどの食品価格が上昇しており、物価上昇率は7カ月連続で3%台となっています。
日銀が重視する「基調物価」も注視が必要な段階に入っています。
アメリカの景気は「減速中だが堅調」
FRBは、2025年上半期の経済成長率が前年より減速したとはいえ、「健全な水準」と評価。
雇用も悪化はしておらず、月平均15万人の雇用増を維持しています。
ただし、内部でも意見は割れており、FRB理事の一部は「景気を下支えするためには、もう利下げが必要」と主張。
判断は難航しています。
政治の影響も無視できない
実は、中央銀行の判断をより複雑にしているのが政治の圧力です。
アメリカ:トランプ氏の発言がFRBに影を落とす
再選を果たしたトランプ大統領は、パウエル議長に対して「今すぐ利下げすべきだ」とSNSで圧力をかけています。
さらに、自身が指名した理事が利下げを支持するなど、金融政策の独立性が揺らぎかねない状況にあります。
日本:参院選敗北で政局不安が日銀を包む
一方、日本では7月の参院選で与党が大敗。石破首相の退陣論が浮上しています。
石破政権は日銀の利上げ方針に理解を示していましたが、もし次に緩和派の政権が誕生すれば、日銀も利上げしにくくなるとの見方が市場に広がっています。
次の動きは9月以降
8月は、FRBも日銀も政策会合が予定されていません。
つまり、次の判断の場は9月中旬。それまでに経済や物価に大きな動きが出れば、対応が遅れるリスクもあります。
各国がパンデミック、インフレ、そして政治的変動と向き合う中で、中央銀行はますます難しいかじ取りを迫られています。
まとめ:動かないことが「最善」のときもある
中央銀行の役割は、「物価の安定」と「経済の安定」という、相反する目標のバランスをとることです。
今は、急いで動くよりも「じっくり見極める」ことが、最善の一手なのかもしれません。
これから秋に向けて、日銀とFRBがどんな判断を下すのか。
政治の動きと合わせて、注目が高まっています。
金融政策は、経済と政治の“鏡”でもあります。
わたしたちの暮らしとどうつながっているのか、ぜひ今後も注目してみてください。