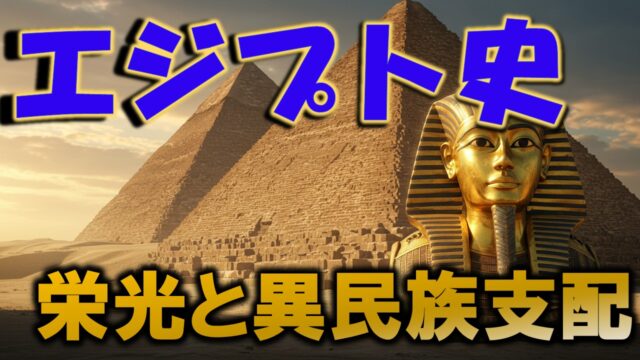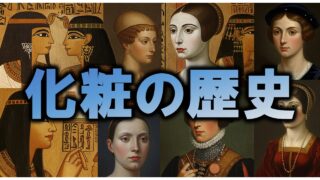皆さん、こんにちは。毎日の食事、当たり前のように楽しんでいますか?
実は、私たちが当たり前だと思っている「一日三食」の習慣や、お米を主食とする食文化には、長い長い歴史があるのをご存知でしょうか。
この記事では、そんな「食事の歴史」を紐解きながら、はるか昔の平安時代から、戦国、そして江戸時代へと、日本人の食生活がどのように変化してきたのかを、皆さんと一緒に旅していきたいと思います。私たちが今、どれほど豊かな食生活を送っているのか、そのルーツを探る旅へ出発しましょう。
1. 平安時代:貴族は豪華、庶民は質素な「食」
今から約1200年前の平安時代、人々の食生活は身分によって大きく異なっていました。
貴族たちは、一日三食を基本とし、中国から伝わった豪華な食事マナーを取り入れた、儀式的な食事を楽しんでいました。彼らの食事には、米の他にも、魚介類や鳥獣肉、野菜、海藻など、様々な食材が使われていました。
一方、庶民の食事は、一日一回から二回と少なく、主食は粟(あわ)や稗(ひえ)などの雑穀が中心でした。食事には、季節の野菜や山菜、魚介類などが使われましたが、貴族のように毎日豪華な食事をすることはできませんでした。
この時代、食事は単なる栄養補給だけでなく、身分や階級を示す重要な役割を担っていたのです。
2. 戦国時代:戦とともにある「食」の進化
平安時代から約400年後、日本は戦国時代へと突入します。戦乱の世では、食の在り方も大きく変わりました。
この時代になると、農耕技術が向上し、米が庶民にも普及し始めました。米は保存がきくため、戦時の兵糧としても重宝されました。また、味噌汁が庶民の間に広まり、手軽な栄養補給源となりました。
武士たちは、戦場で効率よく栄養を摂取するために、乾燥させたご飯を丸めた「干し飯」や、米や野菜などを混ぜて固めた「兵糧丸」といった保存食を携帯していました。
戦国時代の食事は、生き抜くための知恵と工夫が詰まった、実用的なものへと進化していったのです。
3. 江戸時代:「食」の黄金期と新たな課題
江戸時代に入ると、戦乱が終わり、社会が安定したことで、食文化は大きく発展しました。
現代と同じく、一日三食の食習慣が定着しました。特に、白米を主食とする文化が庶民の間で大流行し、白米を大量に食べる習慣が広がりました。
しかし、白米ばかりの食生活には、思わぬ落とし穴がありました。栄養バランスが偏り、ビタミンB1が不足したことで、「脚気(かっけ)」という病気が大流行しました。
また、この時代には七輪(しちりん)が登場し、庶民の家でも焼き魚や焼き野菜が手軽に作れるようになりました。醤油やみりんなどの調味料も普及し、和食の基礎が築かれた時代でもあります。
4. まとめ:現代の食生活は、先人たちの歩みの上に
平安時代の質素な雑穀食から、戦国時代の保存食、そして江戸時代の豊かな食文化まで、日本人の食の歴史は、その時代の社会や文化、人々の暮らしを色濃く反映しています。
私たちが今、当たり前のように享受している「豊かな食生活」は、先人たちが試行錯誤を重ねて築き上げてきた歴史の上に成り立っているのです。
この食事の歴史について、さらに詳しく知りたい方は、こちらの動画も参考にしてみてください。各時代の食生活が、より分かりやすく解説されています。
YouTube動画:食事の歴史について <https://youtu.be/jC1lDGsU68c?si=mHnlWeDZEt130rYq」>